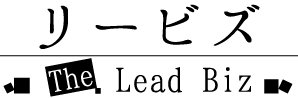【リーダー必読】コーチングとティーチングをマネジメントに生かす方法

ビジネスをしていると「コーチング」「ティ―チング」の言葉をよく耳にしますがその本当の意味を分かっている人は多くありません。あなたはいかがでしょうか?
それぞれの違いを1言で言うと「コーチング」は本人が抱えている問題を引き出し、本当の自分を見つけるためのサポート、「ティーチング」は今ある課題に対しての答えを教えることになります。
実は私自身もよく分かっていませんでした。
それが分かるようになったのは学習塾運営と言う仕事のお蔭です。
塾を運営していく中で、生徒が一番伸びる方法がまさに「コーチング」と「ティーチング」の組合せと言う事にきづきました。どちらかだけでは伸び悩んでいたのです。
そこでもっと深く掘り下げるために「コーチング」や「ティーチング」の本をたくさん読み、学びました。現在では生徒のみならず、講師に対してもこれらの手法を使い円滑な運営が行えています。そういった私の学びを皆さんに活かして欲しく、今回この記事を書いています。
「コーチング」と「ティーチング」を正しく理解し、運用することで部下からの信頼を勝ち取り、スムーズな業務の進行につなげていきましょう。
以下より、詳しく説明していきます。
目次
1. コーチングとは

まず、コーチの認定組織であるICF(国際コーチ連盟)は、このように説明しています。
“コーチングは、クライアントの生活と仕事における可能性を最大限に発揮することを目指し、創造的で刺激的なプロセスを通じ、クライアントに行動を起こさせる、コーチとクライアントとの提携関係を指す”
また、『コーチング・リーダーシップ』(ダイヤモンド社刊)では、コーチングの大きな特徴である「対話」をより前面に出して、こう定義しています。
“対話を重ねることを通して、クライアント(コーチを受ける対象者)が目標達成に必要なスキル、知識、考え方を備え、行動することを支援し、成果を出させるプロセス”
「コーチング」とは人材開発の一つです。
相手の話をよく聞き、「この仕事はどのように進めていきますか?」「今後のスケジュールはどう考えてますか?」など質問をしながら相手のやる気を引き出し、自主的な行動を促すコミュニケーション技術です。
「何かに挑戦したい」「良い結果を出したい」と言う人に効果的です。
理論体系はありませんが対話を通じて心理学やカウンセリング術を使って進めていきます。
1.1. コーチングのメリット
コーチングのメリットは2つあります。
1つ目は自立型人材を育成出来る事です。コーチからの質問により、自ら考えることで、
問題点を見出し、行動し、解決できる自立型人材へと成長します。
2つ目はコミュニケーションの取り方が従来の指示命令系のものから、共生型コミュニケーション(上司からの質問に対し、部下が自ら考えるもの)へと変わることでお互いの理解度が高まり、信頼関係が生まれることです。
私も講師陣の教育にコーチングを活用することにより、始めは言われたことしかできなかった彼らが自ら考え行動できるように変わってきました。
1.2. コーチングのデメリット
コーチングのデメリットは新入社員など経験が少ない人、やる気のない人、スキルのない人には使用しづらいことです。上記の方に無理にコーチングを行うと正しい答えを導き出すことが出来ず混乱してしまします。
また、多人数に対して仕事をしてもらう場合、緊急で急ぐ仕事をしてもらう場合もコーチングでは成果が上がりませんので注意が必要です。
2. ティーチングとは

「ティーチング」とは教える側の人があらかじめ用意した答えをもとに知識や経験の少ない相手に教えていくことです。
具体例で言えば、学校教育がティーチングとなります。学校で勉強を教える先生の事を【ティーチャー】と言いますよね.....
会社組織では新入社員や社歴が少ない社員に対しての指導によく使われます。上司が部下に対して「ここはこうしてみよう!」「その場合はこう考えてみよう!!」と指示することで社員のスキルを上げることが出来ます。
教える側は「なぜ」「何を」「どのように」を具体的に教えながら、ちゃんと理解出来ているかフィードバックを貰うといいでしょう。
2.1. ティーチングのメリット
ティーチングのメリットは先生1に対して、多数の人間を教えることにより同じプロジェクトをする仲間に同じ方向を向かせることが出来ます。先生の引いたレールの上を走らせるように人を動かすこともできるのです。
また、ノウハウを伝授していく場合やマニュアル化が必要な場合のもティーチングの方が上手く進んでいきます。そこにはそれぞれの個性などが必要ないからです。
私も基礎的なことは指導する際にはティーチングの手法でいつも教え込む形をとっています。それにより子供たちの下地が出来上がります。
2.2. ティーチングのデメリット
ティーチングのデメリットは自主性が育ちにくく依存的な傾向が出やすいことです。
これは上司からの一方的なコミュニケーションにより、自主性を促すことが出来ず、部下の自主性を引き出せていないからです。
また、どんなに頑張ってもティーチングでは上司以上の人は育たないため、能力のある人の芽を摘んでしまうことになります。リーダーの資質があってもティーチングだけを学んでいたらみんなと同じ事ばかりで段々とやる気をなくすことになるでしょう。
3. コーチングとティーチングの使い分け方

これまで「コーチング」と「ティーチング」について説明してきました。それぞれにメリット・デメリットがある中でどう使い分けたらいいのか話していきたいと思います。
まず、しなければならないのは相手の状態を出来るだけ正確に把握しておくことです。
具体的に考えてみましょう。入社直後の新入社員であればどちらが有効だと思いますか?「ティーチング」ですよね、、、、入社したばかりの社員には教えることが多くなるのが普通です。
次にビジネススキルの高い中堅社員にはどちらが有効でしょうか?もうお分かりだと思います。「コーチング」が有効になる可能性が高いですね。上から押し付ける目標設定ではなく、自分自身で目標を決めて、達成することでモチベーションアップを図ることが出来ます。
また、若手社員でもやる気があり、仕事の成熟度が高い人には「コーチング」による進め方が大きな成果を生む可能性があります。
逆に、やってはいけないのが明らかに「コーチング」で進めなければいけない人に「ティーチング」で進めていくことです。「コーチング」も「ティーチング」もコミュニケーションの一種ですので使う側の選択が大切になってきます。
4. 部下を育てるコーチングスキルとは

コーチングにより部下を育てる時に一番大切なのは【相手に興味を持つ】事です。 相手に興味を持つことで常に意識が働き、尊重できるようになってきます。また、部下を変えてやろう!!と思う前に自らが変わる意識を持ちましょう。
さらに、コーチングの技術を用いて部下のやる気を出す!と言うのではなく、社員一人一人が楽しく幸せに働ける環境をつくる。というように、視点を制度から人に向けるといいと思います。
そもそもコーチングスキルは150以上あると言われています。そのすべてが次の3つの目的を意識して適用されます。
- 相手の力を発揮させる
- 相手の自律性を促す
- 相手の成長を促進する。
今回コーチングスキルの中で部下を育てるために必要な「信頼関係を築く」「傾聴」「質問」「提案」「承認」の5つについて詳しく説明していきます。
4.1. 信頼関係を築く

あなたは部下と会った初日に信頼関係築けますか?ほとんどの方が無理だと思います。
信頼関係は時間の経過する中で「コツコツ」積み上げていくことが大事です。
そのために必要な魔法の言葉をお知らせしましょう。「なるほど、○○だね」とか「そうだね、○○」を使ってみましょう。逆にNGワードは「いや、○○○」「でも、○○○」は使わないようにして下さい。
そして一番大切なことは【相手の事をすべて知りたい】と思う事です。
4.2. 傾聴

傾聴を辞書で引いてみると【心を集中して聞くこと】と書いてあります。相手の話をただ聞くのではなく、自分の相手に対する先入観を捨てて集中して聞く事が大切です。
また、話している表情やしぐさ、声のトーンなどからも相手の想いを知ることが大事です。耳だけでなく五感をすべて使うつもりで積極的に聞いてください。
現代人は人の話を聞くのがおざなりになっているので慣れるまでは案外難しいと思います。上司と部下で年齢が離れている場合などに気を付けることは「当たり前」の感覚が世代で全然違う事、自分の常識は他人にも常識と思うことは危険だと言う事です。
ここでも一番大切なことは【相手の事をすべて知りたい】と思う事です。
4.3. 質問

コーチングにおける「質問」は一般的に行われているものとは違い、相手の視点を広げたり変えたりすることで気づきを促します。また、現状の問題点をはっきりさせたり目標を設定するのにも有効です。
では、具体的にどの様な質問が効果的だと思いますか?
相手が色んな選択肢をもって答えることが出来るように、「はい」と「いいえ」で答える2択ではなくて、思いを自由に幅広い答え方が出来る質問をしましょう。
理想は質問に答えているうちに自発的に「気づき」や「ひらめき」があることですが結果を急いで矢継ぎ早に質問し、「訊問」になってしまうと逆効果なので注意しましょう。
4.4. 提案

質問から得られた情報を基にこちらから提案していくわけですが、ここでも大切なのはこちらの都合ではなく、相手の成長のために行うこと(相手にとって新しい視点で提供すること)が大事です。
決して結果を急がず、こちらの提案を押し付けないようにしてください。あくまで主体は相手なのでこちらの提案内容を受け入れるかは相手一任です。そのため、提案を受け入れられず断られたりすることもあります。
4.5. 承認

提案を実行するたびに承認をしていきます。承認で大切なことは「加点法」を使うことです。とにかく相手の事を認めてください。その存在、日々の変化を見落とすことなく、まずは小さなところから褒めていきます。
褒める時はYOUメッセージではなく、Iメッセージ、Weメッセージを使いましょう。
具体例を書きます。
YOUメッセージ
上司:「大口契約獲得おめでとう!!お前頑張ったな!!」
YOU(相手)を直接褒める
Iメッセージ
上司:「大口契約おめでとう!!私も本当に嬉しいよ!!」
I(自分)が喜ぶことで相手を褒める
Weメッセージ
上司:「大口契約おめでとう!!会社全体で盛り上がってるぞ!!」
We(その他多数)が喜ぶことで相手を褒める
YOUメッセージの場合、素直に受け入れられない場合もありますが他の2つでは
その心配がありません。主体が自分以外のところにあるからです。
また、相手自身がまだ気づいていないことを先に察知して伝えることで相手はあなたを認め、いい関係が深まるでしょう。
まとめ
みなさん、いかがでしたか?
上司であるあなたが部下の勤務年数等により「コーチング」と「ティーチング」を組み合わせることが一番の近道になります。
あなたが相手の懐に入りこんでいくことで、相手との距離も近くなり、相手も更に心を開くでしょう。
但し、適度な距離感を保ちながら進めることも忘れないでください。
これからのマネジメントに役立つことを願っています。