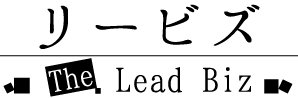アップセルとクロスセルの違いとは?顧客単価を伸ばすコツとは?

アップセルとクロスセルってどう違うの?
上手に活用して顧客単価を伸ばすコツを知りたい!
マーケティング手法の中に「アップセル」と「クロスセル」と呼ばれるものがあります。
どちらも顧客に提案することで購入してもらい、売り上げの向上策として効果を期待できる手法です。
こういった手法がいくつもあるので、「聴いたことはあるけれど、違いが分からない」という人もいるのではないでしょうか。
上手く活用できれば良い効果が期待できますが、間違った使い方をすれば逆効果にもなりかねません。
ここではアップセルとクロスセルの違いを知って、効果のある使い方ができるようになりましょう。
身近な具体例も合わせて紹介していきます。
目次
アップセルとクロスセルとは?
 Original update by:まぽ
Original update by:まぽ
まずは基本です。
アップセルとクロスセルがそれぞれ、どんな手法なのか見ていきましょう。
アップセルとは?
アップセルは顧客の単価を向上させるための営業手法です。
顧客がある商品を検討しているとしたら、現在購入しようとしている商品よりも高額な上位モデルを提案します。
例えば10万円のパソコンを探している顧客にもっと高機能な15万円のパソコンを購入してもらうのもアップセルです。
更に年会費無料のクレジットカードからゴールドカードに変更してもらうのもアップセルの手法ですね。
アップセルの特徴は顧客の購入意欲が高まっている時に商品を販売すると、通常の心理状態よりも販売しやすいという行動心理に基づいています。
アップセルは顧客の購入単価を上げて、絶対の売り上げアップに繋がる方法です。
クロスセルとは?
クロスセルはある商品の購入を検討している顧客に対して、関連する別の商品をおすすめして購入してもらう手法です。
例えばハンバーガーを買った時に、ドリンクやポテトはいかがですか?というのは典型的なクロスセル手法です。
スマホを購入した時にケースや画面保護シートなどの購入を提案するのもクロスセルです。
クロスセルの特徴は新規顧客を獲得するよりも、既存の顧客に追加で購入してもらうことです。
結果、低コストで売り上げを向上させることができます。
本来は買うつもりのなかった商品の購入に繋がり、全体的に見るとより多くの売り上げを得ることが可能になります。
アップセルとクロスセルの違いとは?
次にアップセルとクロスセルの違いを考えてみましょう。
アップセルとは顧客が購入を決めた商品と同じものまたは似たもので、対象商品よりもグレードの高いものを勧めます。
ハンバーガーショップの例でいえば、ポテトのMサイズを注文した際に「今ならLサイズが割引になっていてお得ですが、いかがですか?」とお勧めします。
割引になっているとはいえ、Mサイズのポテトよりは高いものになるので、全体的には売り上げアップとなります。
一方でクロスセルとは顧客が購入を決めた商品とは別の商品をお勧めします。
購入した商品に関連するものを勧めることが多いですが、もちろんそれだけに限りません。
ハンバーガーショップの例だと、ハンバーガーだけを注文したが「一緒にドリンクはいかがですか?」とお勧めします。
顧客が商品の購入を決めるところまでは同じで、そのタイミングなら購買意欲が高まっている心理を利用する点も同じです。
違うのはお勧めする商品が選んだ商品と「同じもの」か、「異なるもの」かという部分です。
顧客単価を伸ばすコツとは?
 Original update by:studiographic
Original update by:studiographic
顧客単価を伸ばすためにはアップセルとクロスセルを使い分けることが有効です。
しかし使い方を間違えると、逆効果にもなってしまいますので、コツを押さえておきましょう。
タイミングが重要
アップセルもクロスセルも、使うタイミングが重要です。
タイミングとしてピッタリなのは、顧客がその商品を買うと決めたその時です。
顧客が「購入します」という意思を固めた直後というのは、お財布が開いている状態です。
購買意欲がほぼ頂点にある時なので、提案をするならこのタイミングを逃してはいけません。
購入を決める前にグイグイと商品を提案してしまうと、顧客に「無理矢理売りつけられそう」「怖い」という印象を与えてしまいます。
この場合はお財布が固く閉じられてしまう可能性もあるので要注意です。
顧客にとって有益であること
アップセルもクロスセルでおすすめする商品は、顧客にとって有益であることが大前提です。
顧客におすすめすることで「便利そう」「これは必要」と思ってもらえればいいのです。
例えば車を購入したら、道に迷わないように「カーナビ」をお勧めする、革靴を購入したら長持ちするように「靴磨きセット」をお勧めするといった具合です。
あくまで提案であって、最終的に購入するかは顧客の判断に任せましょう。
もっといえば提案をしないことで顧客が困ってしまった場合、満足度が下がりあなたやお店への信用も下げてしまう可能性があります。
正しく商品を勧めれば、その時は購入に至らなくても、後で必要になった時に「あの人の言う通りだった」となります。
すると次に提案した時には高い確率で勝ってもらえるようになるのです。
顧客ニーズを満たす品揃え
的確なタイミングでアップセルやクロスセルを行っても、顧客のニーズに合致する商品でなければ意味がありません。
例えばスマホを買った人に「ケース」をお勧めしても、顧客が気に入るデザインのケースがなければ購入には至りません。
確実に購入に繋げるためにも、顧客ニーズを満たす品揃えを徹底しましょう。
アップセルやクロスセルに誘導するには、より上位の商品の存在が不可欠です。
そして顧客が「グレードアップした方が得だ」「合わせて欲しくなった」と認識できるメリットを備えていなければなりません。
もちろん商品の品揃えだけでなく、顧客に分かりやすく説明できるスキルも必要です。
アップセルとクロスセルの具体例とは?
最後にアップセルとクロスセルの具体例を紹介します。
アップセルの具体例
クレジットカード会社は頻繁にアップセルを実施しています。
クレジットカードにはランクがあり、取引実績のある顧客に対して少しずつランクの高いカードへの切り替えを勧めてきます。
最初は年会費無料のクレジットカードを使っていても、年会費1万円のゴールドカードへのランクアップを提案してくるのです。
もちろんゴールドカードには相応の特典がついてきます。
ですから会社側はその利点をアピールしながら、「ゴールドに切り替えた方がお得かも」と思ってもらえるように、アップセルをかけるのです。
パソコンの購入場面でもアップセルは使われています。
最初は「予算8万円のパソコンで」と言っている顧客に対して、その通りの商品を探しながらヒアリングをしていきます。
主にパソコンの用途を聞いたり、仕事に使うなら家で使うのか、外で使うのかも重要です。
例えばゲームが好きで最低限のゲームができればいいという顧客がいたとします。
そこで「画面も美しく臨場感があります。さらに画面が固まることなくストレスなくゲームに没頭できますよ」とお勧めすれば『そっちの方が長い目で見ると良いかも」と考え直してもらえる可能性が高くなります。
このようにアップセルを実現させて、顧客単価を伸ばしているのです。
クロスセルの具体例
お店で購入したものにたいして、関連した別の品物をお勧めする光景は良く見かけます。
1番身近なものではスマホ+スマホケース、携帯充電器、イヤホンなどがあげられますね。
また自転車を購入する場合も、クリーナーやブラシなどの掃除セット、チェーンなどを直す工具や油などをお勧めすることがあるでしょう。
これらは典型的なクロスセル手法です。
また現代ではインターネットでの買い物も一般的になりました。
Amazonや楽天で買い物をしていると、過去の購入履歴や閲覧履歴に基づいたおすすめ商品を表示しています。
また購入後に「こちらの商品を購入した方は、こちらの商品を購入しています」と画面に表示されるのを見たことがある人も多いでしょう。
これもクロスセルを使った手法です。
実店舗だけでなくネットショップでも、取り入れられている手法なのです。
まとめ
いかがでしたか?
アップセル・クロスセルはマーケティング手法のひとつです。
ただし単純にマニュアルに沿って実行すれば良いというものではありません。
どちらにしても大切なのは、顧客が求めているものを提案して満足度を上げることです。
間違った提案をした場合、その時は一時的に売り上げが上がったとしても、顧客からの信用を失い長い目で見ると売り上げを下げることになるからです。
その場しのぎの売り上げを考えるのではなく、長い目で見て、会社全体で見て、顧客単価を向上させるために活用するのがアップセルであり、クロスセルなのです。
正しい方法で活用して、信用度や顧客満足度をアップさせましょう。