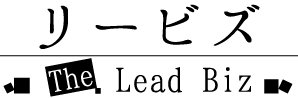独立・起業のベストのタイミングは?退職は何日前に伝える?

独立・起業したいけれど、どのタイミングが1番いいの?
退職時の注意点も知りたい!
サラリーマンから独立して、開業したいと考える人が増えてきました。
しかしサラリーマンを辞めるということは、安定した収入がなくなるということです。
思い付きで独立・開業しても結局、収入を得ることができずに生活ができなくなっては元も子もありません。
独立・開業をするためには、準備が必要ですしどのタイミングで会社を辞めるかなども考える必要があります。
退職となれば、会社に迷惑がかからないように対応することも大人のルールですよね。
ここでは独立・開業を考えている人のベストなタイミングや、退職時の注意点を見ていきましょう。
目次
独立・起業するのにベストなタイミングとは?
 Original update by:すしぱく
Original update by:すしぱく
独立・開業をするためのタイミングは、人それぞれという部分もあります。
ただ何も考えずに思いつきで独立するのはおすすめできません。
ここでは独立・起業をするのに一般的にベストなタイミングをご紹介します。
事業資金(開業資金)を準備する
独立して開業するには、少なからずお金がかかります。
金融会社から借りるという手もありますが、仕事を辞めて資金がない人にお金を貸してくれることはありません。
ですから。独立・起業をするのであれば、ある程度の事業資金を準備しておく必要があります。
その中には起業して1年前後の生活費なども含まれます。
資金は個人によって異なりますが、目安として1000万円はあった方が良いでしょう。
ですから会社員の間に、せめて500万円~1000万円の資金を用意できた段階で、起業のタイミングとする人は多いです。
最低限の人脈を構築する
独立・起業は1人で成し遂げることのように見えますが、実際は人脈がとても重要です。
同じ業界に人脈があるのとないのとでは、その後、業績を伸ばすスピードが違います。
権力のある経営者、上級役員などと関係性があれば、そこで営業ができますし、他の有力者を紹介してもらうこともできます。
人脈がゼロの人が起業をしても失敗するだけなので、ある程度の人脈が出来た時が起業のタイミングと言えます。
準備を整えることが大切
独立して起業するということは、自分で自分の道を切り開いていくことです。
今までは会社に守られていた部分も、すべて自分で対応していかなければなりません。
そして、事業が回らずに稼ぐことができなければ、あなたの収入はゼロになるのです。
独立開業をするということは、様々なリスクが降りかかってくるということです。
ですから現状から逃げたいという、思い付きでの起業は危険であり、様々なリスクを想定した準備が必要なのです。
この準備が整えられたというタイミングで起業することが重要です。
成功できるという確信を持ったとき
独立して起業をする、例え夢だったとしてもやはり不安は付きまといます。
そして「もしかしたら失敗するかも?」「ダメになったらどうしよう」などとマイナス要素を抱えているうちは、実際に起業しても上手くいきません。
例え資金や人脈など準備が整ったとしても、気持ちがついてこなければ失敗を招いてしまうのです。
起業=安定した生活を捨てるということなので、ある程度の気持ちの準備も重要です。
メンタルを強化する、自分のやろうとしている事業に明るい兆しが見えたなど、気持ちも「成功できる」というタイミングで起業した方が成功する確率は高いでしょう。
他人の客観的な判断を仰ぐ
自分1人の意見や考えはどこか、偏ったものになってしまいがちです。
ですから自分で起業のタイミングが決められないのなら、経験者に判断を仰ぐというのも一つの方法です。
これは自分の都合よく考えて判断してしまい、思わぬ失敗に出くわすリスク回避にもなります。
第3者から見て、あなたの考えが甘いのか、理に適っているのか、冷静に判断してもらいましょう。
そして周りの意見にもしっかりと耳を傾けたうえで、「今だ」というタイミングがベストとなるのです。
独立・起業するのにいい年齢は?
独立・起業する際に、年齢という面から考えてみましょう。
まず独立・起業に年齢は関係ありません。
20代のうちにさっさと独立する人もいれば、50代を過ぎてやりたいことが見えてくる人もいるでしょう。
ただ、起業後に何年働くのかを考えると、早い方が良いという意見が多いです。
あえて線を引くとすれば、独立・起業に向いている年齢は、30代です。
30代といえば、会社でもようやく大きな仕事を任せられる段階ですよね。
それに体力があるのでちょっとの無理なら、すぐに回復します。
定年が65歳として35歳で起業すれば30年間、50歳で起業すれば15年間働くことになるのですが、その間、全力で働き続けられるかといえば難しいでしょう。
会社員であれば年齢が上がるほど、体力的には楽な仕事に回してもらうことが多いです。
しかし起業した場合は、自由を手にできても自分が第一線で働く場合が多いですし、開業5年くらいは寝る間もなく全力で働くことになるでしょう。
また最初の事業が上手くいかなくても、若ければ何度でもやり直しができます。
そう考えると、会社員になった20代は真面目に働いて起業資金を貯めていきましょう。
その間にマーケティング、お金、経営の知識を身につける時間にするのです。
そして30代になったら、それまで貯めた資金と知識を武器に、独立・起業するのがベストでしょう。
会社を辞めて独立・起業する際に注意することとは?
 Original update by:きなこもち
Original update by:きなこもち
独立・起業をするということは、会社を辞めることになります。
会社を辞めて独立・起業する際の注意点を見ていきましょう。
退職を伝えるタイミング
会社を辞める場合は、「円満退社」を目指しましょう。
起業後に以前の会社で関わった人と、関わることになる可能性はゼロではありません。
その為にも、退職の意思は早めに伝えることが大切です。
雇用期間が決められていない労働契約であれば、2週間前の申し出により退職できます。
会社によっては1ヶ月前という場合もありますが、これは会社の方針であることが多いです。
できるだけ会社の意向に従うのが良いですが、最低でも2週間前には申し出るということを頭に入れておきましょう。
そしてその際に重要なのが、退職希望日を明確にすることです。
あやふやにしてしまうと、やめる日を引き延ばされる可能性があるので、必ず自分の意思を伝えましょう。
また次の人に引き継ぐ期間も必要なので、引継ぎ期間も含めて、退職を申し出るのが良いです。
自己中心的に辞めることになると、「円満」とはいえなくなるので、早め早めの対応が肝心です。
税金に注意
税金には住民税、所得税、社会保険など様々な種類があります。
会社員の場合、税金は会社の給料から天引きされることになるので、税金について敏感になる必要はありません。
しかし会社を辞めて経営者になるということは、これまで会社が管理していた税金を、自分で管理して納めていくことになります。
この税金のうち起業後に最も注意が必要なのが「住民税」です。
住民税の納付は前年の所得を元に計算され、6月に納付額が決定します。
会社員時代の年収が高い人ほど、住民税が高くなる仕組みです。
また起業後、健康保険を国民健康保険に変更した場合は、健康保険料も前年の年収を元に決められます。
それがとても高く感じられることでしょう。
独身なら良いですが、扶養家族がいる場合は、さらに負担が大きくなるので注意しましょう。
お金の知識をつけておく
税金を始め収入もそうですが、これからは自分でお金の管理をしていくことになります。
ですから、お金の知識はあった方が良いです。
お金の知識が分かるようになる代表的な資格に「簿記」があります。
もちろん簿記1級といった高度な専門知識は必要ではありません。
経営者であれば簿記3級程度の知識があれば十分に対応できます。
簿記会計の基本を把握しておけば、資金調達時に金融機関の融資担当者とも対等な商談ができます。
また顧問税理士との節税対策や確定申告などの密な打合せも可能になるでしょう。
まとめ
いかがでしたか?
独立・起業をしたいのであれば、最低限の準備が必要です。
人脈、資金調達、メンタル、知識、リスク対策など、あらゆる面で準備が整ったタイミングが起業のタイミングです。
また年齢的には、体力がありやり直しが利く30代を目安に始めるのが良いでしょう。
20代は資金を貯める期間、知識を溜める期間として、しっかり下積みを重ねましょう。
会社を退職する際は、円満退職になるように、退職の旨を伝える日や伝え方にも注意が必要です。
一般的に退職希望日の2週間前には、伝えることを忘れずに、会社に迷惑がかからないように配慮しましょう。