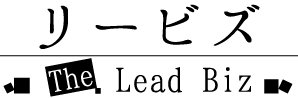仕事で失敗が続く人の4つの共通点とその対処法

仕事に一生懸命取り組んでいるのに上手くいかない。
仲良く仕事をやりたいのに、人間関係でつまずく。
仕事の能力自体はそれほど劣っているとは思わないのに、結果がでない。
そんな仕事に対する漠然とした不安を持っている人は多いと思います。
今回は、述べ3万人のクライアントを持つ現役の心理学カウンセラーという立場から、仕事や事業に失敗しやすい人や、何をやっても上手くいかない人の考え方の癖を心理学的に、わかりやすくご説明してまいりたいと思います。
ご自身や部下、周囲の方々に当てはまるところはないか、確認しながら読み進めていただき、失敗を未然に防ぐことにお役立ていただけたら幸いです。
1.相手の話をじっくり聞けない人

話し手の話を、そのまま受け止めながらじっくりと聴くことを傾聴(ケイチョウ)と言います。
傾聴という概念は、アメリカの臨床心理学者で教育学者のカール・ロジャースという学者が確立しました。日本のカウンセリング理論の基盤を作った学者でもあります。
心理カウンセラーの基本は、傾聴です。
傾聴法は、カウンセリングの現場だけではなく、一般の方の人間関係を良好にするのに大変役立つ方法です。
「相手の話をじっくりと聴く」ということですからこの場合の「きく」は「聞く」ではなく「聴く」です。
「聞く」は音声や言葉として聞こえている意味合いが大きいですが、「聴く」は相手の話す内容を受け入れ相手が何を言いたいかを把握して、次の会話や意見に結び付けていく意味合いが濃いと言えます。
ビジネスのあらゆるシーンにおいて、この「傾聴」が出来ない方がとても多いです。
人の会話の途中に割って入って自分の意見を話し始める人・相手が話しているという事態が不愉快だともろに表情に出ている人・早く相手の会話が終わる事を願っているのがありありと分かる人等など。
遠慮のない関係の夫婦ケンカなどがこの最大のケースかも知れません。
ビジネスにおいてこの傾聴が出来ないと、コミュニケーションが取れないばかりではなく、結局仕事内容の細かいニュアンスなどが、お互い(話し手と聞き手)で理解できず、ともすれば大小様々なミスにつながっていきます。
じっくりと相手の言い分を聴いてあげられる存在にあなたがなれば、あなたの周りには自ずと人が集まることになります。
筆者の友人に、ある大企業の国際部長がいます。
世界的な自動車部品の企業なので国際部長ともなれば、アジアを中心に多国籍の部下を持っていました。
「僕の一番の仕事は待つことだよ。」と彼は言います。
多国籍の部下たちは大変に優秀で、 英語はもちろん日本語もほとんど自由に話せ、5か国語位話す部下もいました。
しかし、やはりネイティブと同じレベルの理解力で、日本語で仕事をしてもらったりするには、ある程度の時間を掛けてこなせるまで「待つしかない」ということです。
自分の仕事はさっさと終わっても、何か仕事をしているふりをして待っていることもあるそう。 勿論、部下がノロノロと仕事をしている場合などは論外ですが、少々イライラしてもまどろっかしくても、待たないと部下は育ちませんし、いつまでも上手くいっていない現状のままです。
傾聴法が出来ない人は、部下の言葉の中に隠れたトラブルの元にも気付きにくいし、どうすれば改善できるかについてのコミュニケーションも取りづらい。
又、傾聴法が下手な人は待つことも出来ない人が多いです。
ここでは、上司が部下の話に耳を傾けるケースを言いましたが、当然の事ながら反対のケースもあります。部下が上司の話に耳を傾けないケースです。
部下が上司の話をきくパターンで圧倒的に多いのが、「聞いてはいる」のですが、「聴いていない」パターンです。
上司が何を言いたいか、何を注意されて何を改善しなければならないか。これは、「聞く」だけでは中々把握できない場合が多いです。
この傾聴法は、何も上司と部下の関係のみに使われるものではありません。家族関係やれないなど様々なシーンにおいて有効です。
ビジネスシーンで言えば、営業時でお客様が何を希望されているのか、又、トラブル回避のリスクマネージメントにも大切な要素となります。是非、取り組んでみてください。
2.鬱(うつ)的なものの考え方をする人

ここで言う「うつ的発想」とは、言葉を変えれば「楽観的発想」と「悲観的発想」の内の「悲観的発想」に物事の考え方が片寄ってしまう人の事を言います。
| 楽観的発想 | 悲観的発想 |
|---|---|
| 明るい | 暗い |
| 楽しい | つまらない |
| 美味しい | まずい |
| 好き | 嫌い |
| 美しい | 醜い |
| 賢い | 馬鹿 |
| 幸福 | 不幸 |
| 成功 | 失敗 |
| 円満 | 破たん |
以上は、物事を楽観的に考える人の発想と悲観的に考える人の発想の一例をあげてみました。
読者の皆さんはご覧になって如何でしょうか?
又、自分はどっち側の傾向が強いと考えるでしょうか?
この文字の羅列に過ぎないものを見て読者はどう感じられるのでしょうか?
筆者は圧倒的に悲観的文字の羅列を気味悪いと感じます。
座右の銘が『アモーレ・マンジャーレ・カンターレ』の筆者は圧倒的に楽観的発想が多いです。言い換えれば、ほぼ能天気。 軽薄とは思いませんがかなり呑気であることは事実と自分を分析しています。
アモーレとは、サッカー選手と女優さんのカップルで有名になった言葉ですが、恋人・愛する人、人を愛する事などの意味があり、マンジャーレは食べること、グルメだけではない、生活ができる(飯が食える)という意味、カンターレは歌うという意味ですが、 筆者は友たちと仲良く歌って(謳歌して)人生を過ごしたいという解釈だと思っています。
楽観的発想と悲観的発想には、それぞれの利点と欠点が有ります。
楽観的発想の人は、それこそ前向きでめげない、陽気などの利点が有りますが、ともすれば調子に乗り過ぎて、自分の姿が見えていないという欠点が有ります。
悲観的発想の人は、 冷静に物事を判断でき道を踏み外しにくいという利点が有りますが、 いつも物事をいぶかって考え、悪い方からの防衛が基盤でものを考えるので、はっきり言ってあまり幸福な気分で人生を生きているとは言い難い人が多いようです。
心の中でいつも最悪の事を考え、用意周到に事を運び・・・ 疲れると思いますし、うつ的な発想から本当のうつ病に突入される方もいます。
そしてその暗さは周りの方にも感染し、「何だかあの人といると疲れるね。」という人物評価につながっていきます。 又、他人からの評価だけではなく、自分で自分の評価を厳しくし過ぎて自己肯定感が低い方が多く見られます。
楽観的という言葉は、ともすれば単にへらへらして物事を考えていないように取られかねませんが、筆者がお勧めする楽観的とは、あくまでもうつ的な発想を止め、前向き・建設的な精神状態で仕事に取り組み、且つ、可能な限り冷静な判断で難関を突破していく、そういったイメージです。
失敗を恐れ、石橋を叩いて叩いて、壊してしまう・・・ 元も子もありませんね。 時には逆風が吹いても、前向きに陽気に果敢に・・・そういう人の周りには自ずと人も仕事も集まってきます。
3.自分を認知行動療法的にコントロールできない人

認知行動療法。名前を聞くだけで難しそうですね。
読者の方が、プロでもないのにこんなもの出来る訳ないじゃないと思われるのも当然なのですが、実は自分でできることもあるのです。
まず『認知』とは簡単に言えば、「もの事を知ること」です。 ちょっと難しく言えば、「外界からの刺激に対して反応し、認識すること」です。
認知行動療法とは、「間違ったもの事をきちんと把握し、考え方を変えて状態を良くしましょう」という療法です。
それでは、ごく簡単な実例でご紹介しましょう。
あなたは、来週の金曜日に会社の新製品のプレゼンを長年の取引先でやらなければなりません。今日は、前の週の金曜日です。後1週間以上も有ります。ゆっくり考えて書きたいと思います。 それに今日はプレミアムフライデー。大学の同級生たちとの飲み会もあるので、プレゼン資料は明日からゆっくり書きたいと思います。どんなにかかっても、土・日2日あれば十分楽勝です。
土曜日。あなたは昨日飲み過ぎてしまいました。頭はガンガンするし、胸やけ・胃腸の調子もよくありません。
日曜日。本当だったら二日酔いはいくら何でもそろそろ良くなるはずですが、逆になんだか余計に具合が悪いです。微熱も有ります。そう言えば、向かいの席に座っていた○○君がいやに咳をしていました。ひょっとしたら、風邪がうつったのかもしれません。しかしまだ日曜日。勤務帰宅後に書いても、月・火・水・木と4日も有ります。出来ると思います。
月曜日。微熱どころか発熱してきました。会社も休みました。明日から書きます。ちょっと時間は厳しいけど。火曜日も欠勤しました。プレゼン資料の事を考えると余計に具合が悪くなってきます。どうしようどうしよう・・・
水曜日、なんとか出勤はしましたが、プレゼン資料はまだ全然書けていません。 風邪の問題ではなく、もう僕には書けないのかも知れません。実力がないのです。この前失敗したのを今度のプレゼンで取り返そうと思っていたのに、もうダメです。資料の構成もあれほど考えたのに、もう頭が真っ白です・・・
木曜日。とうとうプレゼンの前日になりました。相変わらず、1行も書けてはいません。もう時間がありません。上司の鬼瓦のような顔が目に浮かびます。上司からは見捨てられるでしょう。同僚の失笑が聞こえてくるようで、そうなると、ますます書けなくなってしまいます。
ここまで読んで、読者の方はお気づきかと思いますが、「どうしよう・・書けない。実力がない。見捨てられる。笑われれる・・」という事を考えている時間がいかに無駄かという事に気が付いて1行でも書きだすことが大事なのです。
頭の中で囚われている「できない」という認知が間違っていることに気付き、切り替えて始めることが大切なのです。
これが、自分でできる簡単な認知行動療法です。難しいことではなく、自分の抱えている色々な問題点に当てはめることができます。
この間違った認知を切り替えることができたら、今までフリーズして出来なかったことも随分と出来るようになります。何よりも2章で紹介した「うつ的な発想」も切り替えることができるので、随分とあなた自身が前向きに、能動的にお仕事が出来るようになるはずです。特別の訓練などは要りません。切り替えるだけです。
又、何か独自のツールを作っておくのも良しです。
例えば、うつ的な発想になって来たとか、間違った認識(認知)に 囚われたままその考えから離れられない・・・などの場合、この音楽を聴いたらパッと気が晴れるとか、このタレントさんの顔を見たらハッピーになるでも、勿論モチベーションとしている家族の写真とか、目標・夢を書いたものを見る、何でも構いません。試してみて下さい。
4.自己一致出来ない人

自己一致が出来ない人とは、理想の自分と現実の自分があまりに掛け離れている人、またはその状態になっている人の事言います。
理想の自分はどんどん昇進し、報酬も上げてそれを元手に起業し、35歳の時点では、プチホリエモンや孫正義、三木谷になっているはずの自分だったのに、実際には、ついこの間、主任に昇進したばかり。給料も入社以来、そんなに変わらず…。
何で?おかしい!ムカつく!イライラする。
俺が悪いんじゃない、周りが見る目がないんだ!と怒りを周囲にぶつけたくなる。
これが「自己一致できない人」の特徴です。
自己一致できないのにはいくつか理由が有ります。
- 全くもって無茶な計画を立てている
- 何とか頑張れば出来る範囲だが、努力が出来ていない
- 自分の希望とする自己概念にずれが生じてきた
- どこまで進んでも満足できない
離れている理想の自分と現実の自分を近づける、もっと言えば、理想の自分の円内に現実の自分を入れることが出来たら、あなたの仕事のモチベーションも、あなたに対する周りの評価も上がるはずです。

上の図のようにあなたの状態を近づけるにはいくつか方法が有ります。
- 必要なことを準備する。例えば今まで実現できなかった資格を計画的に必ず取っていくとか、必要な勉強に計画的に時間も資金も自己投資していく。
- 理想の自分の状態にズレがないか、無理がないか、現実味があるのか常に確認を怠らない。
- ズレがないか等、信頼できる第3者に確認してもらう。
- 今の自分の恵まれていることに感謝出来ているか確認。
等、理想の自分に近づけていくには、やはり戦略が必要なのです。
そのためには、まず、現実の自分と理想の自分とのギャップを正しく認識するところから始める必要があります。
まとめ
いかがでしたか?
仕事で失敗が続く人の4つの共通点とその対処法について心理学的視点から述べてみました。
大事なことは「現状を知る」ということです。
己の姿が分からなければ、努力する方向も改善点も分かりません。
もちろん、仕事で失敗が続く人の心理学的な問題点はこれだけではありません。
不安神経症・強迫神経症・あがり症・片付けられない症候群等々いっぱいあります。
しかし今回は、割とどんな人でも心の内側に持っていがちな考え方の癖を4つ選んでみました。
もし、思い当たることがひとつでもあれば、少しずつでも自分を変える努力を続けていただきたいと思います。
あなたの人生のプロデューサーはあなたしかいないのですから。健闘を祈ります。