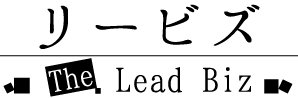アンケートの作り方!項目の作り方や質問例とは?

アンケートってどう作ったらいいの?
しっかり回答をもらうためのアンケートにはコツがあるって本当?
ユーザーのリアルな意見や感想などを聞きたい時に役に立つのがアンケートです。
視聴者アンケートや顧客満足度アンケートなど、様々なシーンでアンケートが実施されています。
そこで集められたデータを元に、改善したり修正しながらより良い方向を目指して行くのです。
結果を出すためにはアンケートをどう作っていくかという部分が非常に重要になります。
ここではアンケートを作る際に考えなければならない「項目の作り方」や「質問例」を見ていきましょう。
また、アンケートを作る上でのポイントもご紹介します。
目次
アンケートを実施するメリットとは?
 Original update by:たかやん
Original update by:たかやん
ネットショッピングでの買い物時、街頭アンケート、セミナーや講義の最後に配られるアンケートなど、誰でも一度はアンケートに出会ったことがあると思います。
サービスに対するユーザーの意見を把握するためには、アンケートの実施が身近なツールとなっています。
アンケートを実施することで得られるメリットのひとつに、提供しているサービスの改善点に気づき修正できることがあげられるでしょう。
サービスを提供する側だけでは気づくことができない部分は必ずあります。
アンケートによって意見を集めることでサービスを受ける側目線の意見を取りいれることが可能になります。
例えばこれを社員1人1人がユーザーに直接質問して聞いていたら、どれだけの工数と費用がかかるでしょうか。
きっと社員が何人いても足りないでしょう。
アンケートを実施することで、同時に大人数への調査が可能になり、大規模な調査をすることができます。
また費用も安く済むので、頻繁に調査を行うことも可能です。
アンケートは効率よく安価でユーザーの意見を集めるのに適しているというメリットがあります。
アンケート作成のポイントとは?
アンケートで良質な情報を集めるには、アンケート作成の段階が重要です。
アンケートを作成する時は、どのようなポイントがあるのでしょうか。
ペルソナを設定する
まず設定して欲しいのが、「誰にアンケートを実施するのか」という「誰に」の部分です。
例えば小学生を対象にしたアンケートと、新社会人を対象にするアンケートであれば、文章構成や表現を変える必要があります。
小学生はひらがな中心の分かりやすい言葉にしますし、新社会人はちょっとしたビジネス用語が入っても問題ありません。
これは極端な例ですが、アンケートを実施する時は対象ユーザーと目線を合わせて、コミュニケーションを取るという感覚が重要です。
そのためにもまずは「誰に」というペルソナを設定することから始めましょう。
質問内容はシンプルに
アンケートの基本はシンプルな質問を載せることです。
質問が長いと人によっては理解できなかったり、途中で読むのをやめてしまう可能性があります。
誰にでも分かりやすい言葉で、シンプルに質問することが大前提です。
特にたくさんのユーザーから回答が欲しい場合は、シンプルであればあるほど応えてくれる回答数も増えます。
もっと限定した相手に実施するアンケートであれば、少し込み入った内容にしても問題ありません。
質問項目は少なめにする
アンケートのページを開いたら、文字がたくさん並んでいて上から下までズラーッと質問事項が並んでいたらどうでしょう。
そのアンケートを読むこと自体、面倒になりませんか。
アンケート作成者からすると聞きたいことがたくさんあるので、次から次へと質問事項が増えてしまいます。
しかし回答者から見れば、文字で埋め尽くされたアンケートは答える気になりません。
アンケートの回答が欲しいなら、的を絞った質問だけを並べるのが効果的です。
同じことを何度も質問していないか、似通った内容になっていないかなど、良く精査して本当に必要な項目に絞り込んで質問事項を少なくしましょう。
アンケート項目の作り方とは?
 Original update by:はむぱん
Original update by:はむぱん
それでは具体的なアンケート項目の作り方です。
ポイントは大きく3点あります。
①ターゲット層のニーズを考える
②ユーザーの本音をつかむ
③原因追及のための質問を入れる
すべて大切な事なので、ひとつずつ見ていきましょう。
①ターゲット層のニーズを考える
アンケート結果を具体的な施策に落とし込むためには、ターゲット層のニーズを考えましょう。
ターゲットがどのような課題を抱えているのかを明確にしなければ、それに対する質問項目もぼんやりしたものになってしまうからです。
またターゲット層のニーズに合わない質問事項ばかりでアンケートを実施しても欲しい答えは得られません。
更にはターゲット層からの支持を失ってしまう可能性も出てきます。
ターゲット層が何に価値を感じていて、どのように考えているのかを把握した上で、項目を考えていきましょう。
②調査目的にあった評価指標を選ぶ
アンケートによってユーザーの本音をつかむためには、まず何を評価するのかを決めましょう。
そしてどのような指標を使って評価するかを考えます。
ここでポイントになるのが「調査目的にあった評価指標を選ぶ」ということです。
例えば顧客満足度を調査するアンケートでは、満足度について質問をします。
しかし顧客がどの程度満足していて継続的に購入してくれるのか、良い口コミを広めてくれるかなどについては、単純な満足度調査では得られません。
より収益に繋がる行動と関係が強い指標を活用することが良いと言えるでしょう。
③原因追及のための質問を入れる
何についての調査を行うのかが決まったら、その指標の数値を変動させる要因を特定します。
そして具体的な改善策を導くための質問を考えましょう。
例えば飲食店の満足度調査であれば、
- 店舗の外観や内装の雰囲気
- メニューの豊富さ
- 食事の味
- 接客・立地など
様々な要因が影響を与えている可能性があります。
このお店の満足度にどの要因が大きく影響しているかを特定できなければ、効果的な改善を考えるのは難しいです。
このようにアンケートの質問を考える時は、可能な限り要素を洗い出すことがポイントです。
アンケートの質問例とは?
最後にアンケートの質問例を見ていきましょう。
ついやってしまいがちな言い回しや表現があるので注意してくださいね。
回答者に合わせた言葉づかいを意識する
アンケートでは全体的にシンプルで直接的な言い回しにすることは重要です。
さらにターゲットのレベルに合わせた言葉遣いに気を付けましょう。
「この宅配ベーカリーに入会したいと思いますか?」
いきなりこの質問では「宅配ベーカリーって?」と何のことなのか詳細が伝わりません。
もっと分かりやすい質問にしましょう。
「宅配ベーカリーは、新作の焼きたてパンを毎週日曜日の朝9時に直接お届けする焼きたてパン宅配サービスです。この宅配ベーカリーに入会したいと思いますか?」
これで質問の背景が見えてくるので、「なるほど」となり回答しやすくなります。
質問はひとつずつ
一度に複数の質問をしてしまうと、回答が面倒になります。
また質問した側も回答を解釈するのが難しくなるので、どちらにもメリットはありません。
「セミナーの構成や興味深さはいかがでしたか?」
これでは「構成」と「興味深さ」の2つの質問が入っています。
ユーザーが一言「まぁまぁ」と答えたら、どう受け取るべきなのか迷ってしまいますね。
「セミナーの構成はいかがでしたか?セミナー内容は興味深かったですか?」
このように2つに分けることで、答える側も質問する側も混乱を防ぐことができます。
バランスも大切
アンケートの中には、回答者を求める回答に導くような質問をしていることがあります。
するとアンケートの客観性が失われアンケートが偏ったものになってしまいます。
「当社のサポート担当者は非常に優秀であると考えています。当社のサポートサービスはどれほど優秀であると思われますか?」
これでは高評価をつけるよう回答者を誘導しているような質問です。
結果、本心からではない高評価を集めることに繋がってしまいます。
「平均的に考えて、当社のサポートサービスはどれほどお客様のお役に立っていますか?」
こうすることで、他社と比較することができますし、バランスのとれた公平な質問になります。
結果、回答者の真の声を聞くことができます。
まとめ
いかがでしたか?
たかがアンケートと思うかもしれませんが、作成する段階が最も重要です。
適当なアンケートを作成して、結果欲しい情報が何も得られなかったでは、無駄な時間になってしまいます。
「誰に」「何を」聞きたいのかはもちろんですが、ターゲットのニーズは何なのか、調査目的にあった評価指標を選んでいるかなど考える必要があります。
また回答者側の立場に立って、シンプルかつ絞られた質問で構成されたアンケートを作成しましょう。
少しでも「面倒だな」と思われれば、ユーザーの真の答えは見えてきません。
アンケート作成時の手間のかけ方次第で、その後の改善点や課題が見えてくるのです。